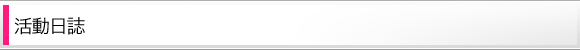令和8年(2026年)の活動日誌
仙台市消防出初式

1月6日,恒例の仙台市消防出初式が挙行され出席してまいりました。明治27年5月,明治10年以来の町火消が生まれ変わり新しい組織として180人の公設消防組が仙台市に設置され現在に至っております。消防職員1.140名・消防車両240台・ヘリコプター2機を有し日夜市民の安心安全のために活動頂いております。近年の火災件数は減少傾向でありましたが令和7年は前年(247件)を上回り253件と増加に転じております,また,救急出動件数も増加傾向にあり令和7年は速報値で過去最多の66,812件(前年比1,378件増)と4年連続で過去最多を更新しました。これは1日あたり183件の救急出動がある状況です。こうした状況の中でも日々訓練を重ね仙台市民の安心・安全のために取り組んでいる消防職員ならびに消防団のみなさまに敬意を表します。
今年一番最初の公務へ出席

1月5日,仙台市中央卸売市場の「業務開始式」に出席してまいりました。水産物は取扱金額で前年比92.8%取扱数量で87.7%,青果については同様に97.1%と90.9%と低調ぎみであるものの,食肉においては取扱金額で105.9%取扱数量で101.4%と順調に推移しております。仙台卸売市場引き続き109万市民の台所として食の安定供給に努めて頂きたいと思います。また,花き市場は昭和48年11月5日に中央卸売市場における全国初の花き市場として農林水産大臣の認可を受けた歴史ある市場とのことです。引き続き「花」で仙台市民の笑顔をつくって頂きたいと思います。